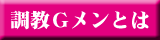
-
☆調教の種類は運動の種類と同じ分類
運動には重量挙げや短距離走のように短時間で全力を出しきる無酸素運動と、ジョギングやマラソンのようにゆっくりと長時間行う有酸素運動があります。
競馬はというと、かつてはスプリント戦は無酸素で走るとされてきましたが、近年の研究により、そうではないことが明らかになりました。
競走馬は1ハロン15秒までは完全な有酸素運動で走るようです。では、15秒より速くなると完全な無酸素運動かというとそうでもなく、全力疾走になる前までは有酸素と無酸素を同時に使わなければならないのです。もちろん、スピードが速くなればなるほど、無酸素運動の比率が高くなります。つまり、日本の平均的なレースの形は、道中では有酸素運動の比率が高く、ゴール前では完全な無酸素運動になっているのです。
『調教Gメン』ではこの2種類の走りの配分が距離、競馬場、レース条件によって違うことに注目してきました。つまり、有酸素運動を中心に行っているゾーンと無酸素運動を行っているゾーンの占める距離、位置によって、レースの適性は大幅に変わるというわけです。そして、各馬の適性能力を決定づけるのが「調教」なのです。
☆無酸素ゾーンが長いレース「秋華賞」
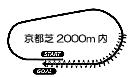 秋華賞の場合、スタートしてまもなく1コーナーとなりレースはスロー(有酸素運動が中心)で流れます。ただ内回りということもあり、後続は3コーナーすぎから早目に仕掛けます(無酸素運動の比率が高くなる)。結果3角から始まった無酸素運動はゴール前まで要求され、無酸素運動を重点に鍛えられている坂路スパルタ型が結果を残します。
秋華賞の場合、スタートしてまもなく1コーナーとなりレースはスロー(有酸素運動が中心)で流れます。ただ内回りということもあり、後続は3コーナーすぎから早目に仕掛けます(無酸素運動の比率が高くなる)。結果3角から始まった無酸素運動はゴール前まで要求され、無酸素運動を重点に鍛えられている坂路スパルタ型が結果を残します。
具体的な例でいうと99年の秋華賞でしょう。1番人気のトゥザヴィクトリーが番手で追走したこともあり、有力馬をこれを目標にして早目の仕掛けとなりました。この結果ゴールまでの無酸素ゾーンが広くなり、坂路スパルタ調教で無酸素運動に長けていたブゼンキャンドルが差し切ったというわけです。2000年も無酸素運動に適した坂路型のテイエムオーシャンとローズバドのワンツーでした。
☆無酸素ゾーンが短いレース「菊花賞」
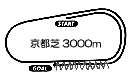 長距離という大前提で、騎手が手探りの流れ(有酸素)で始まります。スパートに関しても京都外回りという点から早仕掛けを嫌い(有酸素)、直線を向いてからのGOサイン(無酸素)となるわけで、有酸素運動的な効果が大きいウッド調教馬が活躍します。その傾向は流れがミドルペースより速くなれば、より顕著になります。3強時代だった99年はウッド調教馬のナリタトップロードが快勝。坂路軽目型と菊花賞には適さない調教だったダービー馬アドマイヤベガは惨敗しています。
長距離という大前提で、騎手が手探りの流れ(有酸素)で始まります。スパートに関しても京都外回りという点から早仕掛けを嫌い(有酸素)、直線を向いてからのGOサイン(無酸素)となるわけで、有酸素運動的な効果が大きいウッド調教馬が活躍します。その傾向は流れがミドルペースより速くなれば、より顕著になります。3強時代だった99年はウッド調教馬のナリタトップロードが快勝。坂路軽目型と菊花賞には適さない調教だったダービー馬アドマイヤベガは惨敗しています。
☆無酸素ゾーンが長くも短くもないレース「天皇賞秋」
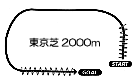 馬場が広くコーナーの少ない天皇賞秋は、距離が同じでも秋華賞とはまったく違った調教が求められます。スタートしてからすぐのコーナーを過ぎると、長いストレッチでは激しい先行争い(無酸素)が展開され、その後は長い直線を考慮に入れて流れが落ち着きます(有酸素)が、直線ではゴール前の坂越え(無酸素)が待っているといったコース形態になっているため、有酸素運動的なウッド調教はもちろんのこと、無酸素運動的な部分をフォローする坂路調教併用馬が結果を残すというわけです。直前予想でアグネスデジタルを◎に推したのは典型的な前記パターンだったからです。2着もウッド調教主体の坂路併用型だったテイエムオペラオーで決まったことで天皇賞の傾向はより明らかになりました。
馬場が広くコーナーの少ない天皇賞秋は、距離が同じでも秋華賞とはまったく違った調教が求められます。スタートしてからすぐのコーナーを過ぎると、長いストレッチでは激しい先行争い(無酸素)が展開され、その後は長い直線を考慮に入れて流れが落ち着きます(有酸素)が、直線ではゴール前の坂越え(無酸素)が待っているといったコース形態になっているため、有酸素運動的なウッド調教はもちろんのこと、無酸素運動的な部分をフォローする坂路調教併用馬が結果を残すというわけです。直前予想でアグネスデジタルを◎に推したのは典型的な前記パターンだったからです。2着もウッド調教主体の坂路併用型だったテイエムオペラオーで決まったことで天皇賞の傾向はより明らかになりました。
☆条件に適した調教をみつけよう
このように施行条件により求められる運動の種類は違います。つまり膨大な調教データベースから検証された事実と競走馬研究者の研究結果からレースに適したトレーニングを課されている馬(=勝ち馬)を明らかにした必勝法が『調教Gメン』というわけです。
- コース区分
-
レース週に追いきった調教コースで区分
- 調教系区分
-
- スパルタ
- 週平均1本以上の調教でしかも追い状態に「一杯」系の表記が多い馬
- 乗込
- 週平均1本以上の調教で追い状態に「馬ナリ」系の表記が多い馬
- 急仕上げ
- 週平均1本未満の調教で追い状態に「一杯」系の表記が多い馬
- 軽目
- 週平均1本未満の調教でしかも追い状態に「馬ナリ」系の表記が多い馬
- 標準
- 週平均1本程度の調教で追い状態に「強目」系の表記が多い馬
- 標準少め
- 週平均1本未満の調教で追い状態が「強目」系の表記が多い馬
- 標準多め
- 週平均1本以上の調教で追い状態が「強目」系の表記が多い馬
- 一杯平均
- 週平均1本程度の調教で追い状態が「一杯」系の表記が多い馬
- 馬ナリ平均
- 週平均1本程度の調教で追い状態に「馬ナリ」系の表記が多い馬
なお競馬王1月号に掲載のあった内容には誤りがあり、ここに記載している区分定義が正しいものです。ここに訂正とお詫びを申し上げます。
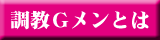
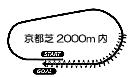 秋華賞の場合、スタートしてまもなく1コーナーとなりレースはスロー(有酸素運動が中心)で流れます。ただ内回りということもあり、後続は3コーナーすぎから早目に仕掛けます(無酸素運動の比率が高くなる)。結果3角から始まった無酸素運動はゴール前まで要求され、無酸素運動を重点に鍛えられている坂路スパルタ型が結果を残します。
秋華賞の場合、スタートしてまもなく1コーナーとなりレースはスロー(有酸素運動が中心)で流れます。ただ内回りということもあり、後続は3コーナーすぎから早目に仕掛けます(無酸素運動の比率が高くなる)。結果3角から始まった無酸素運動はゴール前まで要求され、無酸素運動を重点に鍛えられている坂路スパルタ型が結果を残します。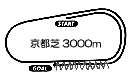 長距離という大前提で、騎手が手探りの流れ(有酸素)で始まります。スパートに関しても京都外回りという点から早仕掛けを嫌い(有酸素)、直線を向いてからのGOサイン(無酸素)となるわけで、有酸素運動的な効果が大きいウッド調教馬が活躍します。その傾向は流れがミドルペースより速くなれば、より顕著になります。3強時代だった99年はウッド調教馬のナリタトップロードが快勝。坂路軽目型と菊花賞には適さない調教だったダービー馬アドマイヤベガは惨敗しています。
長距離という大前提で、騎手が手探りの流れ(有酸素)で始まります。スパートに関しても京都外回りという点から早仕掛けを嫌い(有酸素)、直線を向いてからのGOサイン(無酸素)となるわけで、有酸素運動的な効果が大きいウッド調教馬が活躍します。その傾向は流れがミドルペースより速くなれば、より顕著になります。3強時代だった99年はウッド調教馬のナリタトップロードが快勝。坂路軽目型と菊花賞には適さない調教だったダービー馬アドマイヤベガは惨敗しています。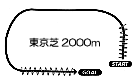 馬場が広くコーナーの少ない天皇賞秋は、距離が同じでも秋華賞とはまったく違った調教が求められます。スタートしてからすぐのコーナーを過ぎると、長いストレッチでは激しい先行争い(無酸素)が展開され、その後は長い直線を考慮に入れて流れが落ち着きます(有酸素)が、直線ではゴール前の坂越え(無酸素)が待っているといったコース形態になっているため、有酸素運動的なウッド調教はもちろんのこと、無酸素運動的な部分をフォローする坂路調教併用馬が結果を残すというわけです。直前予想でアグネスデジタルを◎に推したのは典型的な前記パターンだったからです。2着もウッド調教主体の坂路併用型だったテイエムオペラオーで決まったことで天皇賞の傾向はより明らかになりました。
馬場が広くコーナーの少ない天皇賞秋は、距離が同じでも秋華賞とはまったく違った調教が求められます。スタートしてからすぐのコーナーを過ぎると、長いストレッチでは激しい先行争い(無酸素)が展開され、その後は長い直線を考慮に入れて流れが落ち着きます(有酸素)が、直線ではゴール前の坂越え(無酸素)が待っているといったコース形態になっているため、有酸素運動的なウッド調教はもちろんのこと、無酸素運動的な部分をフォローする坂路調教併用馬が結果を残すというわけです。直前予想でアグネスデジタルを◎に推したのは典型的な前記パターンだったからです。2着もウッド調教主体の坂路併用型だったテイエムオペラオーで決まったことで天皇賞の傾向はより明らかになりました。